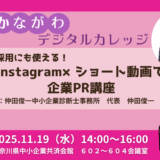横浜中華街発展会協同組合(以下、「発展会」)は、横浜中華街の発展のために活動する協同組合です。中華街内の飲食店をはじめとした各種店舗、地元事業者等が加盟し、円滑な商業活動のためルールづくり・催事やイベントの運営などを行っています。今回は発展会が取組む人流データの活用についてお話をおうかがいしました。
【きっかけ】コロナ禍で横浜中華街への誹謗・中傷が問題に
2020年当時、新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、横浜中華街では心ない中傷や、感染拡大と中華街を結び付けたような根拠のない噂や風評が流れていました。また感染拡大の影響により、中華街の来街者が激減し、平日の営業を自粛したり、臨時休業を余儀なくされたお店も多くありました。このような状況に危機感を持った発展会では、以前から導入していた「人流データ」に着目。街に人が集中していないこと、感染対策を徹底していることをデータを通して発信し、安心して訪れてもらえるよう働きかけを行いました。

人流データとは 「いつ・どこから・どこへ」人が移動しているのか、あるいは「どこに・どのくらい滞在しているのか」といった人の動きを、位置情報データを元に取得したデータのこと
【活用】データを“見える化”して地域の信頼を獲得。「横浜春節祭」でも大きな力に
当時、人流データの取得には年間で約100万円ほどの費用がかかっていました(現在はプランの見直しにより大幅にコストダウン)。「取得しているデータを、どう活かすか」という議論もありましたが、この誹謗中傷の問題を機に、データが街の信頼を守る手段となることに気づいたといいます。その後、人流データは“街づくりの武器”として、さまざまな場面で活用されていきました。
たとえば「横浜春節祭」の立ち上げの際。中華街の賑わいを広く横浜のまちに広げたいと企画された「横浜春節祭」ですが、周辺の商店街や自治体に協力を呼びかける際に、人流データを根拠に集客の効果や地域への波及効果を示して説得しました。こうした地道な説明が功を奏し、現在では主催団体を横浜春節祭実行委員会に移し、横浜市のバックアップのもと、企業や団体との連携も広がり、来場者数は期間中で約840万人にもなる一大イベントへと成長しています。
【展望】“肌感覚”を“データ”で裏付ける。見えてきた課題と次の一手
現在、発展会では人流データを「肌感覚を裏付ける客観的な情報」として活用しています。たとえば、年代別の来街者を見てみると、20代と50代が多いことが分かりました。街を歩いているのは食べ歩き目的の20代が中心であるのに対して、ゆっくりレストランで食事を楽しむ50代の姿も多く見られており、こうした傾向がデータからも読み取れます。
また「夜は人が少ない」と思われがちな中華街ですが、データでは実はそうでもありません。確かに通りを歩く人は減りますが、店内で食事を楽しんでいる方が多く、「夜は滞在型の来街者が中心」であることが分かります。
人流データに限らず、データから色々なことが見えてきます。例えば、駐車場の利用時間の調査では駐車時間が平均1.5時間程度でした。これは、レストランに入っていない、つまり食べ歩き利用の人が多いのではないか?という仮説が立ち「どうすればレストランに人を呼び込めるか」「人が流れていないところの回遊性をどうあげるか」課題が明確になり、議論に繋がっていくわけです。

中華街は生き残るために時代の変化を捉えて街の形を変えてきた“トランスフォーメーションの街”でもあります。生活の場としての町から、中華料理街、そして観光の街へと変遷を遂げてきました。今後は中華街が横浜観光のゲートウェイ(玄関口)となるように、一層街を盛り上げていきたいといいます。 データを巧みに活用しながら日々進化を続ける横浜中華街に、これからも注目です。